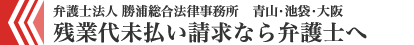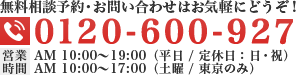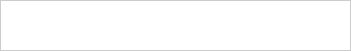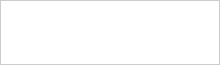労働基準法では、管理監督者は残業代支払いの対象外とされています(但し、管理監督者にも深夜割増賃金は発生します)。
ここでいう管理監督者とは「経営者と一体的な立場にある従業員」のことを指します。管理監督者として認められるためには、それにふさわしい権限・裁量・待遇を有している必要があります。
では、管理監督者にふさわしい待遇とは、具体的にどの程度の金額なのでしょうか。
今回は管理監督者の判断基準の一つである「待遇」という面に焦点を当て、その目安となる金額について解説します。
目次
管理監督者とは
労働基準法では「監督若しくは管理の地位にある者」、すなわち管理監督者には、時間外労働や休日出勤における割増賃金の支払いが適用されない旨が記されています。
簡単に言えば、基本的に管理監督者には残業代が支給されないのです。(深夜割増手当を除く)
それでは、一体どんな人が管理監督者に該当するのでしょうか。
一般的に、管理監督者性の判断は、主に下記の3つの要素を考慮して行われます。
・事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限が認められていること
・自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
・一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇が与えられていること
(参考:厚生労働省「労基法41条2号の管理監督者の該当性」)
つまり管理監督者とは、経営者と一体的な立場にあり、経営や労務に関する一定の決定権や自己の労働時間に対する裁量を有していると同時に、一般労働者と比べ賃金上の優遇を受けている者を指します。
具体的な業務実態の例としては、経営方針に口出しをできる権利がある、従業員の評価や採用に深く関与している、本人が始業時間に遅刻しても注意を受けるようなことはない、などが挙げられるでしょう。
管理監督者にふさわしい待遇の「相場」
前述のとおり、「地位と権限にふさわしい待遇(賃金上の処遇)を受けていること」は、管理監督者の該当性を判断する要素のひとつです。
では、管理監督者にふさわしい待遇とは、具体的にどの程度の賃金を指すのでしょうか。
管理監督者にふさわしい待遇としての賃金額は、その会社の給与形態や水準、仕事量や責任の重さなどによって異なるため、明確な「相場」を述べることはできません。
ただし過去の判例を見ると、一定の目安となり得る傾向が伺えます。例えば、次のような裁判例があります。
・年収891万円は客観的に高額ではなく、その他事情を加味しても管理監督者とは認められないと判断された事例
(大阪地裁令和2年12月17日判決 労働判例ジャーナル109号22頁「福屋不動産販売事件」)
・管理手当4万円は高額ではなく、その他事情を加味しても管理監督者とは認められないと判断された事例
(東京地裁令和3年6月30日判決 労働判例ジャーナル116号40頁「三誠産業事件」)
判例を踏まえると、管理監督者として認められるには、「単に周囲よりもやや高い程度」では不十分であり、「客観的に見て高待遇である」と言える必要がある、という傾向があります。
次章からは、上記2つの判例について、詳しく解説します。
管理監督者の給与の目安がわかる裁判例
ここからは、管理監督者にふさわしい待遇(給与)の目安を判断するのに役立つ裁判例を2つご紹介します。
①年収891万円は客観的に高額ではないとされたケース
令和2年に大阪地裁で争われた、比較的新しい判例です。
不動産の売買・賃貸・仲介・管理を行う会社にて、異なる店舗でそれぞれマネージャー(店長)として働いていた従業員(A・Bとする)が、支払われるべき残業代が支払われていないとして、会社に対し残業代請求を行いました。
このケースでは、給与面での管理監督者性の有無が大きな争点となり、最終的に裁判所はA・B両者の管理監督者性を否定しました。
給与に関する裁判所の具体的な見解は以下です。
・A・Bの7万円の役職手当は、管理職ではないアシスタントマネージャーの役職手当3万円に比して、その差額が管理監督者としてふさわしい金額であるとはいえない。
・Aの約891万円の年収は、同従業員よりも高額ではあるものの、客観的に特に高額であるとまではいえず、業務内容や権限・責任の重要性を考慮しても、管理監督者であったとは認められない。
・Bの約1,166万円の年収は、同従業員に比して高額であった。ただし業務内容や権限・責任の重要性については管理監督者にふさわしいものとまではいえない。
このケースでは、Aの年収が管理監督者にふさわしいものではないと判断されたのに対し、Bの年収は相応であると判断されています。このことから、管理監督者性が認められるためには、客観的にみて高い水準の年収と、他の従業員との十分な差が必要になることがわかります。
(参考:大阪地裁令和2年12月17日判決 労働判例ジャーナル109号22頁「福屋不動産販売事件」)
②役職手当4万円は高額ではないとされたケース
こちらも令和3年に東京地裁にて争われた、新しい判例です。
ビルや住宅の建材の加工・販売・施工を行う会社で働いていた従業員が、定年後に再雇用された際の未払い残業代の支払いなどを求め、会社に対し請求を行いました。
会社側は「従業員は管理監督者であるため残業代の支払い義務はない」と主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。
裁判所が管理監督者性を否定した要素は複数ありましたが、特に給与面では以下のように述べています。
・原告は月4万円の役職手当を受けていた。しかし「この手当があるから労働時間の規制を外しても問題ない」といえるほどの待遇が与えられていたとは認められない。
このケースでは、月4万円という額では、管理監督者性を認めるには不十分であると判断されています。①、②で紹介した判決を踏まえると、「数万円の手当では管理監督者にふさわしい待遇とはいえない」という傾向が見受けられます。
(参考:東京地裁令和3年6月30日判決 労働判例ジャーナル116号40頁「三誠産業事件」)
管理監督者性の否定要素になるケース
管理監督者性は、給与面では以下のような要素によって否定される可能性があります。
下記のケースに複数当てはまるような場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
ケース①:一般職と給与が逆転している
一般職と給与が逆転していることは、管理監督者性を否定する上で非常に重要な要素となります。
管理監督者は重要な職務内容や責任を担うため、一般職よりも高額な給与が支払われるのは当然でしょう。
それにもかかわらず、一般職が受け取る給与(残業代含む)が管理監督者の給与(残業代は支払われない)よりも高く、「給与の逆転現象」が起きているような場合、その待遇は「管理監督者にふさわしいもの」であるとはいえず、管理監督者性は否定される可能性が高いです。
ケース②:客観的に給与が高額でない
客観的に見て受け取っている給与が高額ではない場合も、管理監督者性が否定される傾向にあります。
ただ、「管理監督者性を認めるために十分な給与額」は、業務内容や権限などによっても上下するものであると考えられますので、一概にいくら以下なら管理監督者性が否定されるという基準があるわけではありません。
実際に管理監督者性を判断する際には、一度労働問題に精通した弁護士に相談し、専門的な見解を仰ぐことをおすすめします。
ケース③:管理監督者以外にも役職手当が支給されている
管理職の方が役職手当を受けている例は多く見られます。この手当は、賃金上の優遇として、管理監督者性を満たす要素になり得ます。
ただし、管理監督者以外にも役職手当が支給されている場合には注意が必要です。
前述の判例「①年収891万円は客観的に高額ではないとされたケース」でご紹介したように、他の従業員も役職手当を受けており、かつその金額の差がさして大きくない場合には、「管理監督者とみなせる十分な賃金が与えられている」とは認められず、管理監督者性が否定される可能性があります。
少額の役職手当を与えることにより、あたかも管理監督者であるかのように見せかけようとする会社は少なくありません。「自分は管理監督者ではないかも?」と少しでも感じた場合は、まず弁護士へ相談することをおすすめします。
「名ばかり管理職」の方が残業代を請求する手順
業務や待遇の実態が管理監督者に該当しないにもかかわらず、「管理職だから」という理由で、残業代が支払われないなどの不利益を被っている状態を「名ばかり管理職」と呼びます。自分の状況が名ばかり管理職に該当する場合には、以下の手順によって、会社に対し未払い残業代を請求することが可能です。
1.弁護士へ相談
未払い残業代の請求にあたっては、まず労働問題を扱う弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、必要な法的手続きをサポートしてもらうことができ、労働者本人の負担は大きく軽減されます。
弁護士を選ぶ際には、費用や相性はもちろん、残業代請求の実績が豊富かどうかも重視するようにしましょう。
残業代請求に強い弁護士の選び方は、下記の記事で詳しく解説しています。
残業代請求を依頼する弁護士の選び方|弁護士費用等を解説
2.証拠の収集と残業代の計算
残業代請求にあたっては、タイムカードや勤怠管理データなど、残業の事実やその時間を示す証拠が必要です。証拠が手元にないという方は、弁護士に依頼することで会社に証拠の開示請求を行うことが可能です。
手元にある証拠が少ないという場合は、下記の記事を参考に証拠を集めましょう。
残業代を請求したいけど証拠がない場合の対処法|証拠になるものを詳しく解説
証拠を収集したら、それをもとに請求する残業代の具体的な金額を算出し、会社に内容証明郵便を送って、未払いになっている残業代の支払いを求めます。
3.会社との交渉
会社の反応次第では、会社との任意交渉を行います。
この交渉は弁護士に代理を任せることができるため、労働者自身が会社の担当者と直接顔を合わせる必要はありません。
4.労働審判・訴訟を提起する
相談者の状況や手元にある証拠、会社の反応などを総合的に判断し、今後の方針を決めます。その後の選択肢としては、労働審判または訴訟が一般的です。
労働審判は、短期間で双方の合意による解決を目指す手続きです。労働審判の場合、1〜3ヶ月程度で合意に至るケースが多いです。
一方で裁判は、お互いの主張・証拠をもって徹底的に争う場所です。裁判の場合は、早ければ半年、複雑な事件であれば1年以上かかることもあります。
どちらを選ぶべきかに関しては、相談者の状況や現状の証拠を踏まえて、個別に判断します。労働審判にも裁判にも、それぞれメリット・デメリットがありますので、気になる方は下記の記事をご覧ください。
「名ばかり管理職」の残業代請求は勝浦総合法律事務所へ相談を
管理監督者の要素を満たしていないのに「名ばかり管理職」として扱われ、残業代なしで時間外労働を強いられているという場合には、会社に対し未払い残業代を請求すべきです。
未払い残業代請求の手続きは、勝浦総合法律事務所へご依頼ください。残業代請求の実績豊富な弁護士が、初期費用0円の完全成功報酬制で、一連の手続きをサポートします。
相談料は無料です。残業代請求について疑問や不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。
監修弁護士
 執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
「解決したはいいけど、費用の方が高くついた!」ということのないように、残業代請求については初期費用0円かつ完全成功報酬制となっております。成果がなければ弁護士報酬は0円です。お気軽にご相談ください。