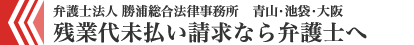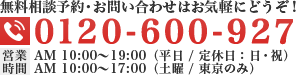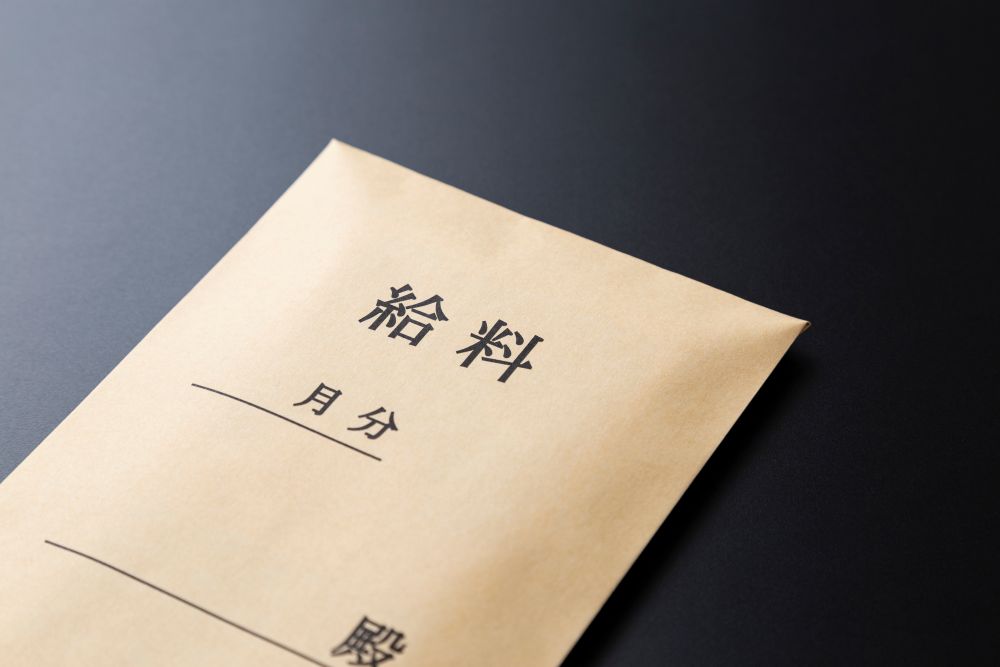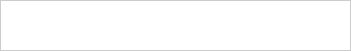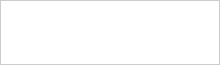みなし残業代(固定残業代)とは、「毎月一定時間分の残業代を、あらかじめ給料に含めて支払う制度」のことを指します。
実際の残業時間に関係なく一定の残業代を受け取れるという点においては、労働者にとってメリットになり得る制度です。
しかし「会社がみなし残業代を勝手に撤廃して、給料が減った」という声も少なくありません。
そこで今回は、労働者の合意なしにみなし残業代が廃止され、結果として労働者の受け取る給料が減った場合の違法性や不利益変更などについて、わかりやすく解説します。
目次
合意なく勝手にみなし残業を廃止するのは違法か?
結論から言うと、「みなし残業の廃止が不利益変更に当たり、かつ労働者の合意がない、または合意があっても変更の合理性が十分でない」という場合は違法です。
労働契約法第9条では、会社は労働者の合意なしに、不利益な条件変更をすることはできないと定めています。
また同法第10条では、変更の合意がない場合でも、就業規則の変更が周知され、かつ合理的な内容であるときには、労働条件を変更できるとしています。裏を返すと、周知や合理性といった要件を満たしていない場合には違法であり、会社の変更は無効とされることがあります。
不利益変更に当たる可能性のあるケース
固定残業代制度の廃止は、不利益変更にあたることが多いです。
例えば下記のようなケースに当てはまり、それが給与減につながっていれば不利益変更にあたります。
・固定残業代制度がなくなり、実労働での残業代支給に切り替わった
・固定残業代の代わりに、売り上げに応じた歩合給が導入された
・固定残業代が廃止され、能力に応じた技術手当に置き換わった
これらの変更によって、従業員の給与が以前よりも減少する場合には、労働契約上の不利益変更に該当する可能性があります。
特に固定残業代制度では、一定額の残業代が毎月支給されることが保障されています。
これが廃止されて成果や能力に連動した制度へと移行すると、給与額が人や時期によって変動しやすくなり、結果として給与が減少することもあるでしょう。このような場合も、不利益変更と判断される可能性があります。
不利益変更の認否における主な判断要素
みなし残業代の廃止などの労働条件の変更が、労働契約法上の不利益変更に該当するかどうかの判断では、以下の点が重視されます。
・労働者の合意の有無
・不利益変更の合理性
各ポイントについて詳しくみていきましょう。
労働者の合意の有無
労働契約法第9条では、労働者に不利益となる労働条件の変更を行うには、原則として労働者の合意が必要であると定められています。
また、その合意が有効と認められるためには、労働者の自由な意思に基づいてなされたかどうかが重要な判断要素となります。
しかも、労働者の自由な意思に基づいてなされたといえるためには、その変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する必要がある(最二小判平成28年2月19日民集70巻2号123頁、最二小判昭和48.1.19民集27巻1号27頁)と考えられています。
ですから、例えば「合意しなければ解雇する」といった圧力がかかっていた場合には、形式的にサインしていたとしても、その合意は無効と判断される可能性がありますし、そのような強制がなかったとしても、従業員にメリットの全くない不利益変更については、仮に従業員が同意書にサインしていたとしても、無効となる可能性が高いです。
また労働条件の変更後、労働者が異議を述べないまま給与を受け取り続けた場合でも、ただちに「黙示の合意があった」とは認められないとした判例もあります(NEXX事件 東京地裁 平成24年2月27日 全基連 ID:08903)。
不利益変更の合理性
労働者に不利益となる労働条件の変更を行うときには、原則として合意が必要です。ただしその変更が就業規則の変更によりなされて、周知されており、かつ合理的であれば、必ずしも合意が必要ではないと定められています。(労働契約法第10条)
判例を見ると、不利益変更の合理性の有無は、以下のような要素から判断される傾向にあります。
・労働者にとっての不利益の程度(影響の大きさ・深刻さ)
・労働条件を変更する業務上・経営上の必要性
・変更後の就業規則の内容が社会通念上妥当といえるか
・労働組合との事前協議・説明の有無
・その他、就業規則変更に至るまでの経緯や背景事情(手続の適正性や代替措置の有無など)
例えば、「大曲市農協事件」という判例では、農協の合併に伴い退職金制度が見直された結果、一部の職員にとって退職金の支給倍率が引き下げられるという不利益が生じました。
しかし最高裁は、給与水準の改善や定年延長などの措置が取られていたこと、退職金格差の是正が合併後の人事管理上やむを得ないものであったことなどを踏まえ、就業規則の変更には合理性があり、有効であると判断しました。
(大曲市農協事件 最判昭和63年2月16日全基連 ID:03924)
このように、不利益変更が有効とされるには、単なる業務上の都合ではなく、客観的かつ具体的な事情に基づく合理的理由が必要です。
合理性の有無は、個別事案ごとに多面的に評価されることになります。
不利益変更の認否が争点になった判例
ここからは、不利益変更の認否が争点となった具体的な判例を3つご紹介します。
NEXX事件
【概要】
電気機器やシステム開発・販売を行う会社に勤務していたXは、業績不振を理由に、会社から給料を20%減額された。Xは減額された給料を3年間受け取り続けたが、やがて解雇され、その後会社に対し、給料の減額が違法な不利益変更であったとして、損害賠償と賃金減額分の支払いを求める裁判を起こした。
【ポイント】
・Xは減額に異議を唱えず、減額された給料を受け取り続けた
・給料の大幅減額にかかわらず、会社側の説明や緩和措置は不十分であった
【判決】
裁判所は、「異議を唱えなかったからといって黙示の合意は認められない」「特に今回のような大幅な減額の場合、合理的説明や緩和措置は必須である」として、賃金の減額は無効であると判決を下しました。
(NEXX事件 東京地裁 平成24年2月27日 全基連 ID:08903)
山梨県民信用組合事件
【概要】
ある信用組合が合併し、合併後に退職金の支払い基準の変更(引き下げ)を行なった。
以前からその信用組合に勤務しており、退職金の支給を求めた労働者らは、この変更を違法であるとして、提訴した。
一審・二審では、信用組合側の主張のとおり、変更に際して労働者らは同意していたと認定し、原告の請求を棄却した。
【ポイント】
・退職金という賃金に関わる変更である
・労働組合との労働協約によって変更が有効になった
【判決】
最高裁は、「退職金のような重要な労働条件については慎重な同意の確認が必要であり、労働者らが署名押印した同意書が自由な意思に基づいていかどうかの審理は十分にされていない」また「労働組合の執行委員長に協約締結の権限があったか不明である」として、労働者側の主張を認め、原審を破棄・差戻ししました。
(山梨県民信用組合事件 最判平成28年2月19日 全基連 ID:09093)
公共社会福祉事業協会事件
【概要】
旧・公共社会福祉事業協会で勤務していたXらは、新たに事業を受け継いだ社会福祉法人に継続雇用されていた。労働組合と社会福祉法人との間では、「当面の間、現行の労働条件を遵守し、変更の前には協議を行う」旨が約束されていた。
その後、社会福祉法人は就業規則を変更。Xらは基本給の変更には合意したものの、各種手当の変更については不利益変更であるとして合意せず、差額の支払いを求めて訴訟を提起した。
【ポイント】
・会社は変わったが、事業はそのまま引き継がれている
・当面の旧労働条件の遵守の旨が約束されている
・労働者は諸手当の変更のみ合意せず
【判決】
裁判所は、「事業を承継するということは雇用契約も承継するということであり、当面の旧労働条件の遵守の旨も確認されていることから、新たな賃金制度を適用するには合意や合理的理由が必要である」また「諸手当の減額分は経営合理化に寄与する程度が低い」として、各手当の不利益変更について、その一部を否定しました。
(公共社会福祉事業協会事件 大阪地裁 平成12年8月25日 全基連 ID:07596)
既に減額に合意してしまっている場合は?
合意した契約がすべて有効になるとは限りません。
形式上の合意があったとしても、真に自由な意思に基づくものではないと判断される場合には、その契約は無効となる可能性があります(民法第96条)。
実務的には、賃金や退職金の減額といった経済的な影響のある不利益変更については、仮に形式上の合意があったとしても、「労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在」(最二小判平成28年2月19日民集70巻2号123頁、最二小判昭和48.1.19民集27巻1号27頁)しないという理由で無効とできることが大半です。
また、労働契約の内容が労働基準法や労働協約、就業規則などに違反している場合、たとえ合意していたとしても、その違反部分は無効とされます(労働基準法第13条)。
例えば、合意の結果として給与が最低賃金を下回るという場合、その部分の合意は無効です。
まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
そもそも、そのみなし残業代は本当に有効ですか?
そもそも、みなし残業代制度が適法に運用されていないケースも少なくありません。
制度として導入するには、会社側が以下の要件を遵守する必要があります。
・みなし残業代に関する取り決めが就業規則や労働契約書に明記されていること
・固定給のうちどの部分がみなし残業代に該当するのか(金額・何時間分)が明記されていること
上記の要件を満たさない場合、そのみなし残業代制は無効となります。
このような場合、支払われた固定給はすべて「基本給」とみなされ、残業代が別途支払われていないことになります。したがって、労働者は会社に対して未払い残業代を請求できる可能性があります。
みなし残業代の要件については、「固定残業代(みなし残業代)を超えた残業代は請求できます。」にて詳しく解説しています。
残業代請求の事例【勝浦総合法律事務所】
みなし残業代制度の要件が遵守されていない場合、無効と判断され、追加で残業代を請求できる可能性があります。例として、当事務所が対応したケースをご紹介します。
40代の男性営業職の方が、残業代請求のご相談に来られました。
勤務先の会社は、「基本給に20時間分の残業代が含まれている」と主張し、それ以上の残業代の支払いを拒否していました。
しかし、基本給のどの部分がみなし残業代に当たるかが明記されておらず、弊所弁護士は、そもそもみなし残業代制が無効であることを指摘。
粘り強く交渉を重ね、190万円の回収に成功しました。
固定残業代については最高裁の判例が数多くあり、労働者に有利な判決になることが多いです。
みなし残業代に関する残業代請求は弊所へ相談を
「みなし残業代の廃止により給与がカットされてしまった」
「みなし残業代が他の給与に置き換わり、最終的な給料が減ってしまった」
このような残業代に関するお悩みは、勝浦総合法律事務所へご相談ください。年間7.8億円もの残業代請求実績を持つ弁護士が、会社の対応の違法性を見極め、未払いの賃金・残業代請求をサポートします。
弊所では、初期費用0円の料金体系を採用しており、残業代請求に成功しなければ費用はいただきません。残業代にお悩みの方は、まずは無料相談をご利用ください。
監修弁護士
 執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
「解決したはいいけど、費用の方が高くついた!」ということのないように、残業代請求については初期費用0円かつ完全成功報酬制となっております。
成果がなければ弁護士報酬は0円です。お気軽にご相談ください。