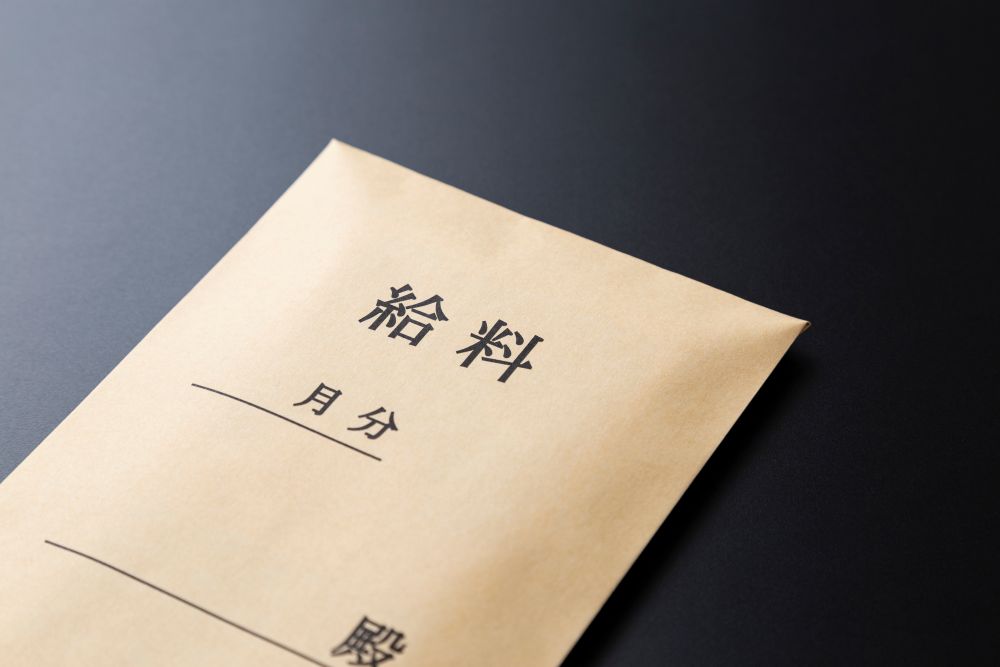事故がきっかけとなり、トラックドライバーを辞める方は少なくありません。
「このまま続けていたら人身事故に繋がるかもしれない。」「自分の命が危険になるかもしれない。」
そんな思いで、退職を検討される方もいるでしょう。
しかし、実際に会社へ退職を申し出ると、「退職するなら過去に起こした事故の賠償金を払ってください」「払い終わるまで辞められません」と言われ、辞めさせてもらえないケースがあるようです。
では、会社に属するトラックドライバーが運送業務中に事故を起こした場合、その損害賠償はドライバーが自腹で負担すべきなのでしょうか。
今回は、運送会社で働くトラックドライバーが事故を起こした場合の損害賠償について、わかりやすく解説します。
目次
「払い終わるまで辞められない」は本当か
運送業で事故を起こしてしまった際、トラック運転手が会社から「損害賠償を払い終わるまで辞めることはできない」と言われることがあります。しかし、これは法的には正しくありません。
民法627条1項では「期間の定めのない労働契約の場合、労働者はいつでも退職の申し入れをすることができ、申し入れから2週間が経過すれば退職できる」ということが定められています。
この2週間という予告期間を、使用者のために延長することは許されないとした裁判例があります(高野メリヤス事件 東地判昭和51年10月29日全基連 ID:00425)。
したがって、事故を起こしたトラック運転手に対し、会社が「損害賠償を払い終わるまで辞めることはできない」とすることは違法です。
損害の全額を労働者が負担する必要はない
運送会社に勤務するトラックドライバーが事故を起こし損害を出した場合、そのドライバーがすべての損害賠償を自己負担する必要はありません。
過去の判例から傾向を見ると、ドライバーの軽度な過失などによって発生した事故について、そのドライバー自身が負う賠償責任は5〜30%程度になることが多いです。
法律では、会社の使用者責任(民法第715条)が定められていますが、その一環として「報償責任」という考え方があります。これは、「事業活動によって利益を得る者は、その活動によって生じた損失も負担すべきである」という考え方です。つまり、運送業で利益を得る会社は、業務によって生じた損失も負担すべきであると解されるのです。
この点を踏まえても、事故を起こした場合に、トラックドライバーが車両の修理費用や第三者への損害賠償など、すべての賠償責任を自腹で負担する必要はありません。
もしすべての損害賠償を負担するよう求められているのであれば、それは不当であるとして、会社と交渉する余地が十分にあります。
逆に未払い残業代を請求して「帳消し」にできる可能性も
事故によって発生する損害は、非常に大きな金額になることがあります。そのうちの何割かを労働者が賠償する場合、ケースによっては、その負担が数十万、数百万という金額になることも少なくはありません。
そこで確認したいのが、未払い残業代の有無です。
もし未払いの残業代があれば、会社に対し残業代を請求し、その残業代請求額で損害賠償を「帳消し」にできる可能性があります。また、未払い残業代の金額が大きい場合、損害賠償額を差し引いてプラスになることもあるでしょう。
実際に、弊所に相談に来られたドライバーの方の中で「勤務中の事故を理由に、会社から150万円の損害賠償請求を受けている」という方がいらっしゃいました。
このケースでは、未払いになっていた残業代の200万円を会社へ請求し、結果として会社への支払いを相殺できました。(トラックドライバーの残業代請求の事例はこちら)
弁護士に相談すれば、未払い残業代の請求手続きはもちろん、「そもそもその損害賠償請求は正当かどうか」「支払う必要は本当にあるのかどうか」の判断についてアドバイスを受けることができます。
まずは勝浦総合法律事務所にご相談ください。(相談料・着手金は0円ですので、お気軽にお問い合わせください。)
事故後の給料の天引きは違法か?
トラックドライバーが事故を起こした場合、会社がドライバーの同意なしに給料から損害額を天引きすることは、原則として違法です。
これは労働基準法第24条にて「税金や社会保険料などの法定控除を除き、賃金はその全額を労働者に直接支払わなければならない」と定められている、いわゆる「賃金全額払いの原則」によるものです。
労働者の同意なく損害額を給料から差し引くことは、この原則に反しており認められません。
また、仮に書面や口頭で同意した場合でも、その同意が労働者の自由な意思に基づいたものであるという客観的な証拠がなければ、後に無効と判断される可能性があります。
ただし会社が支給している「無事故手当」については、事故を起こした場合に減額や不支給となることがあります。これは賃金の減額ではなく、支給条件を満たさなかったことによる不支給という扱いであり、就業規則に明記されていれば法的に認められる可能性があります。
無事故手当の扱いについては、自社の就業規則や賃金規程をよく確認しておきましょう。
誓約書にサインしてしまっている場合は?
基本的には労働者にとって明らかに不利益がある誓約書については、例えサインしてしまっていたとしても無効になることがあります。場合に分けて見てみましょう。
・事故の前に、一律の損害賠償を約束させる誓約書
入社時にもらう雇用契約書などに「業務中に事故を起こした場合、違約金を〇〇円支払う」「損害額の◯%を労働者が支払う」などと記載されていることがあります。
このような取り決めは労働基準法16条に違反するため、無効とされる可能性が高いです。
・事故の後に、一定期間退職しないことを約束させる誓約書
「修理代を分割で払うかわりに、返済が終わるまで退職しない」「5年間は退職しない」などの取り決めも、労働者の退職の自由を不当に制限するものです。
民法第627条では退職自由の原則が認められており、こうした拘束は無効となる可能性が高いです。
・事故の後に、損害賠償金の全額負担を求める誓約書
ドライバーの過失があるとはいえ、全額自己負担を一方的に求める内容は、過剰で不公平とされます。
判例でも運転手が事故を起こした場合、本人の過失割合に応じて損害の5~30%程度の負担にとどめる判断が多く、全額を認める裁判例はほとんどありません。
したがって、このような誓約書も無効とされる可能性が高いでしょう。
・事故の後に、損害賠償金の一部負担を求める契約
これは労働者と会社の間で交わされる私人間の合意と扱われ、負担割合や賠償額によっては有効とされる可能性もあります。
ただし、労働者の自由意志によってサインをしたことが分かる証拠がなければ、無効になることもあります。
このように誓約書があってもすべてが有効になるわけではなく、記載内容や状況によっては無効と主張できます。自身にとって不利益な誓約書をサインさせられた場合は、まずは労働基準監督署や弁護士へ相談しましょう。
運送会社の退職時にやるべきこと
事故後に運送会社から退職するときに、会社から事故の損害賠償を請求されていたり未払い残業代がある可能性があったりする場合には、以下の対応を取るようにしましょう。
弁護士に相談する
まずは労働問題を扱う弁護士を探し、「損害賠償請求に正当性があるかどうか」、「未払い残業代が請求できるかどうか」、「未払い残業代によって損害賠償請求の金額を賄うことができるかどうか」などの点について相談しましょう。
法的観点から弁護士の意見を聞き、アドバイスを受けることで、今後の対応の方向性を決めることができます。
会社からの損害賠償請求に正当性がない場合や未払い残業代請求が可能な場合であれば、会社に対する法的手続きについて、弁護士にサポートを受けると良いでしょう。
損害金の根拠を明確にする
会社による損害賠償請求に正当性がある場合でも、請求金額の妥当性については、労働者側でも改めて確認する必要があります。請求額が実際の損害に見合った金額かどうか、弁護士に相談しながら判断しましょう。
例えば、車両の修理代を請求されている場合であれば、修理代の実費と会社・労働者の負担割合をもとに、その金額が算出されていなければなりません。会社に修理代を確認できる領収書の提出を求めるとともに、業務状況や環境を踏まえ会社・労働者の負担割合を調整することも必要でしょう。
支払う損害金を適正な金額で収めるためにも、損害金の根拠(実費や負担割合)は明確にしておくことが大切です。
安易に合意書にサインしない
会社による損害賠償請求の金額や内容に納得できない場合には、無理に合意書にサインする必要はありません。
強引にサインを求められた場合でもサインはせず、会社との交渉を録音するなどして、弁護士へ相談しましょう。
トラックドライバーの労働問題は勝浦総合法律事務所へ相談を
「事故を起こして損害賠償を請求された」「残業代が適切に支払われていない」など、トラックドライバーの労働問題は、勝浦総合法律事務所へご相談ください。
労働問題解決の経験と実績豊富な弁護士が、それぞれの事情に寄り添い、手厚くアドバイスやサポートを行います。
相談料は無料です。
労働問題に関してお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
監修弁護士
 執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
執筆者:勝浦 敦嗣(かつうら あつし)
所属:第二東京弁護士会所属
-監修コメント-
「解決したはいいけど、費用の方が高くついた!」ということのないように、残業代請求については初期費用0円かつ完全成功報酬制となっております。成果がなければ弁護士報酬は0円です。お気軽にご相談ください。