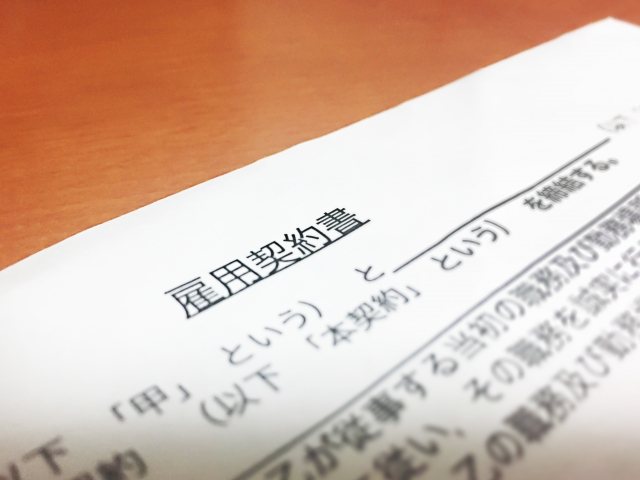
サービス残業ばかりの日々、なんとか残業代請求ができないものか…。そこでふと入社時の雇用契約書を見るとそこには「残業代は支給しないものとする」の文字が!
知らずにサインしてしまったとはいえ、残業代が出ないという契約は果たして有効なのでしょうか?
目次
1.まずは残業代のルールについて理解しよう
契約の有効性を検討する前に、まずは残業代のルールについてご説明しましょう。
「残業」という言葉は、実は法律用語ではありません。
そのため、法律上はふたつの概念が「残業」に該当します。
「法定労働時間外労働」
まずひとつ目は、労働基準法で「法定労働時間外労働」と呼ばれるものです。これは、1日の実労働時間のうち、法定労働時間である8時間をひいた時間のことを指します。
長時間働かせることになるので、いきなり「○時間残業してね」ということはできず、あらかじめ使用者と労働者の間で労働基準法36条を根拠とする残業の協定、いわゆる36(サブロク)協定を結ぶ必要があります。36協定を結ばずに法定労働時間を超えて残業させることは違法となり、会社側は「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という重い刑事罰を受ける可能性があります。
また、法定労働時間外労働にあたると、通常の時給に加えて割増賃金が支払われます(労基法37条)。
「所定労働時間外労働」
もうひとつは「所定労働時間外労働」と呼ばれるものです。別名を「法内超勤」ともいいます。
例えば、アルバイトだとシフトが6時間に設定されていたり、パートのショート勤務で3時間と決められている場合がありますよね。これが「所定労働時間」です。
所定労働時間を超えてはいるものの、法定労働時間の範囲内で労働した部分を「所定労働時間外労働」といいます。
仮に、6時間のシフトのはずが7時間働いてしまった、というように、所定労働時間を超えて働いたとしても、法律上割増賃金はつきません。あくまでも8時間を超えた分が法定労働時間外労働として、割増賃金の対象になるのです。
所定労働時間を超えて働いた分については、割増にはなりませんが、通常の時給が支給されます。また、労働契約書などに、所定労働時間外労働に割増賃金を支払うという規定があれば割増賃金の対象です。
2.労基法(労働基準法)のルールは絶対に守らないといけない
さきほど、「法定労働時間外労働」についての定めが労基法にあるとご説明しました。実は、この労基法とは、一部の例外を除いて絶対に守らなければならないルールなのです。そもそも法律には、任意法規と強行法規というものがあります。
任意法規とは、当事者間の合意によって、法規に優先するルールを定めることができるものです。一方、強行法規とは、当事者の間でどのような約束をしても、必ず法律が優先されるものです。労基法は労働者の生活を守るためのものですから、当事者の約束ですぐに変更できてしまったら意味がないですよね。そこで、一部の例外を除き、労基法の定めは強行法規とされているのです。
実際、労基法にはこのような条文があります。
(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
つまり、労基法に違反する契約は無効になり、代わりに労基法の定めが適用されるのです。
これを残業代の話に置き換えてみましょう。1日8時間を超えた部分について割増賃金を払わなければならないというのは、労基法に定められています。したがって、当事者の契約によっても変更できない、強行法規ということになります。
そのため、雇用契約書に自分でサインしてしまったとしても、「(1日8時間を超えた部分の)残業代を支払わない」という契約は無効になり、きちんと残業代は支払われるのです。
3.法律の落とし穴!所定労働時間に注意
では、所定労働時間外労働については残業代が支払われるのでしょうか。
ここで、所定労働時間外労働は労基法によって定められた労働時間ではありません。あくまで会社が任意で定めたものに過ぎないのです。したがって、この時間については割増賃金の支払いがないどころか、契約内容は当事者に委ねられます。
仮に所定労働時間外労働について、いくら賃金を払うか決めていなかった場合にはどうなるのでしょうか。
この点、行政の通達によれば
「法定労働時間内である限り所定労働時間外の1時間については,別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。但し,労働協約,就業規則等によって,その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差支えない。」(昭和23年11月4日基発1592号)
とされています。つまり、通常払われる時給と同額が支払われるのです。
では、契約書で「残業代を支払わない」とした場合にはどうでしょうか。先ほどの行政通達には「労働協約,就業規則等によって,その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差支えない。」と書かれているだけで、賃金を支払わなければならないとしていません。
また、労基法上もこの点について定めがありません。したがって、残念ながら契約書に「残業代を支払わない」と明示され、これにサイン=同意したとみなされる以上、所定労働時間外労働について残業代は支払われません。ただし、実際の契約書はもっと複雑だと考えられるため、文言解釈について争う余地はあります。
残業代が出ない契約はあるのか
時間外労働をした場合は割増賃金や通常の時給が支給されるということがわかりましたが、そうなると冒頭の「残業代は支給しないものとする」という契約は無効となるのでしょうか?
いくつかのケースごとに内容をみていきましょう。
●一定時間分の残業代が給料に含まれている場合
これは固定残業代の制度で、いわゆる「みなし残業」のことです。
この制度は、あらかじめ労働契約書などで「月30時間までの時間外労働については固定残業代として5万円を支給する」として、毎月の給与や手当の中に一定の残業時間分の手当を固定して支払うという制度です。
みなし残業制度を導入している場合は、みなし残業時間の範囲内であれば残業をしても残業代を請求することはできません。
先ほどの例だと、28時間残業したとすれば請求できないということになります。
一方で、みなし残業代制度は、「一定の残業代を支払っているから」という理由でみなし残業時間を超過していることを見逃されるなど制度を濫用されてしまうことがあります。
先ほどの例だと、実際の残業時間が35時間だった場合、5時間分の超過部分について残業代を請求することが可能です。。
注意していただきたいのは、みなし残業代制度自体が無効となる場合には、実際の残業時間がみなし残業時間の範囲内であったとしても残業代を請求できるケースがあることです。
みなし残業代部分が通常の労働に対する賃金部分と明確に区別され、残業の対価としての性質を有する場合でなければ有効なみなし残業代制とはいえず、会社側は残業代を支払う必要があります。例えば、「残業代は基本給に含む」などという場合は無効となります。
また、想定された残業時間が多すぎる場合にも無効となる場合があります。
勤務先の固定残業代制度が有効であるか疑問をお持ちの方は、一度専門家に相談されてはいかがでしょうか。
●年俸制を採用している場合
年俸制はよく野球選手の契約などで耳にすることがあると思いますが、1年単位で給与を算出する給与体系のことをいいます。まとめて1年分支払われる訳ではなく、労働基準法第24条によって、1ヶ月単位に分割して支払うことと定められています。
成果主義を導入している企業の試みの1つとして採用されることが増えています。
まず前提として、年俸制だからといって直ちに残業代を支払わなくてよいわけではありません。
年俸制であっても、残業代部分が通常の労働に対する賃金部分と明確に区別され、残業の対価としての性質を有する場合でなければなりません。例えば、雇用契約書や就業規則に、「年俸の中には時間外手当を含む」と定められていたとしても無効となります。
●管理監督者の場合
労働基準法41条2項は、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)には労働時間に関する一部の規定を適用しないと定めています。そのため、管理監督者には時間外、休日に関する割増賃金は支払われません。
重要なのは、管理職=管理監督者ではない、という点です。よく問題となるのはいわゆる「名ばかり管理職」で、実際には管理監督者としての権限を与えられていないにもかかわらず、管理職の名前が付いていることによって残業代が支払われていないというものです。
労働基準法上、管理監督者に該当するためには次の条件を満たしていなければなりません。
①重要な職務や権限を有する(経営方針の決定に参加する、自分の裁量の行使権限があるなど)
②労働者の管理監督や指揮命令、採用などの権限がある
③出退勤時刻が自分の裁量に任される(出退勤や勤務時間について管理を受けず自由に決めることができる)
④地位にふさわしい待遇がなされている(職務の重要性に見合う基本給や役職手当が支給されているなど)
これらの条件を満たしていない場合は管理監督者に該当しませんので、残業代をきちんと支払ってもらえることになります。なお、管理監督者に該当する場合でも、深夜割増賃金を請求することはできます。
このように、一定の条件を満たしている場合には残業代を支払わなくても良い場合があります。そのため雇用契約書や就業規則などはきちんと確認することが大切です。
では、そもそも「残業代を支払わないものとする」という契約に合意していたとしたら、「合意しているから支払わないよ」となってしまうのでしょうか?
結論はというと、労働基準法に違反する合意であるため、その契約自体が無効となります。
残業代の支払いは労働基準法に定められた会社の義務であり労働者の権利なのです。







